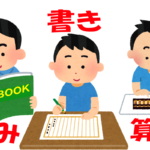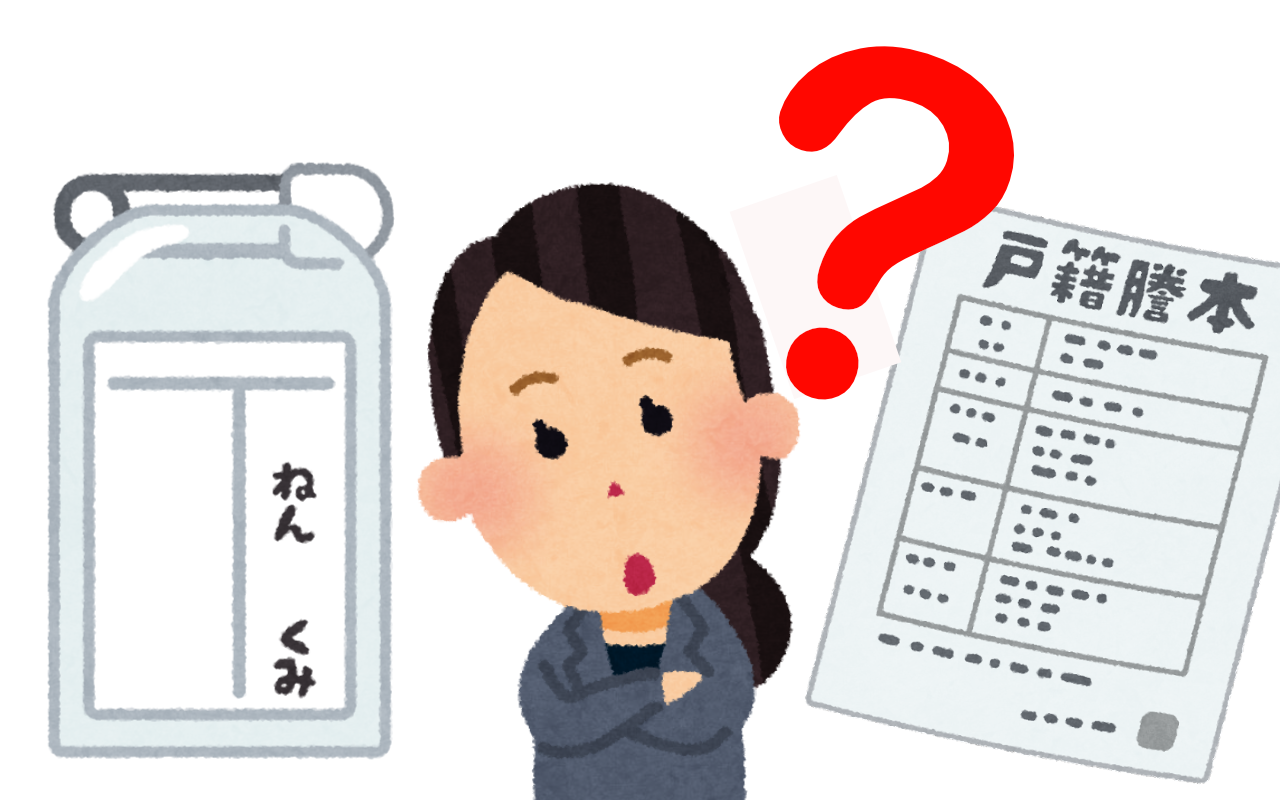
龍ケ崎市の広報誌を見ていてちょっと驚いた。
広報誌には「わがやの天使」というページがある。そこには1歳になる子供たちの写真と名前が載っているのだが、漢字で書かれている名前のほとんどがフリガナがないと読めなかったのだ。
漢字と読み方が結びつかない名前がとにかく多い。
日本語の表記は漢字と仮名で成り立っている。漢字の読み方には訓読みと音読みのふたつがある。
訓読みは漢字が持つ意味を、それに対応する日本語に当てはめた読み方だ。
音読みは漢字が本来持つ音(漢字は中国で発明された文字なので中国語の発音が漢字とセットになっている表語文字)で発音する読み方だ。日本に伝わった時期によって読み方が違うこともあるので(呉音、漢音、唐音がある)外国人が日本の漢字を読むとき(時に日本人でも)苦労するところでもある。
たとえば「読」という漢字は、訓読みでは「よむ・よみ」だが、音読みだと「どく(呉音)・とく、とう(漢音)」となる。
訓読みにせよ音読みの違いがあるものの漢字には決まった読み方がある。
だから書かれている漢字の発音に苦労することは普通はない。
例外として地名や苗字に特殊な読み方をするものがあるが、一度覚えてしまえば問題のないレベルだ。
ところが最近の子供の名前にはどう読んでいいのかわからないものが多い。
こうした名前のことを「キラキラネーム」と呼ぶらしい。
ポータルサイトGooで絶対に読めないキラキラネームというランキングがある。1位から10位までを紹介すると、男(あだむ)、心姫(はあと)、紅葉(めいぷる)、桃花(ぴんく)、夢姫(ぷりん・ゆらり)、天音(そぷら)、奏夢(りずむ)、愛翔(らぶは)、愛羅(てぃあら)、一心(ぴゅあ)。
驚くというより、こんな名前を付けた親の顔が見てみたいというのが率直な感想だ。
鎌倉時代に書かれた「徒然草」の116段に「人の名も、見慣れぬ文字を付かんとする、益なき事なり」というのがあるので、日本人にはこうしたキラキラネームをつける癖があるのだろう。
こうしたキラキラネームが登場した背景に、『たまごクラブ』という雑誌の存在があるらしい。
戸籍法第50条に「子の名には、常用平易な文字を使用しなければならない。」と規定されていて、「常用平易な文字の範囲は法務省が定める」とある。常用平易な文字でないといけないが、その名前をどう読ませるのかについて規定がない。そもそも戸籍の名前にフリガナを書く欄がない。
いっぽう出生届には名前の上の欄に「よみかた」という欄がある。そして漢字で書かれた名前の読み方は親が自由に書くことが出来るようになっている。
つまり「夢」という漢字を「どりーむ」と読んでも「みらい」と読んでも法的には何の問題もないいということだ。
「男」と書いて「あだむ」と読ませるのもわからないわけでもない。
そう考えると日本語の表記は実に融通無礙なものだ。
それにしてもキラキラネームが氾濫すると、「あなたの名前は何と読むの」といちいち訊かなくてはならない学校の先生は大変だ。
ところでこの記事を英訳するのだが、ちゃんと意味が通じるだろうか?
ちょっと心配だ。