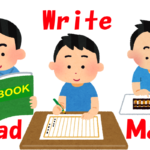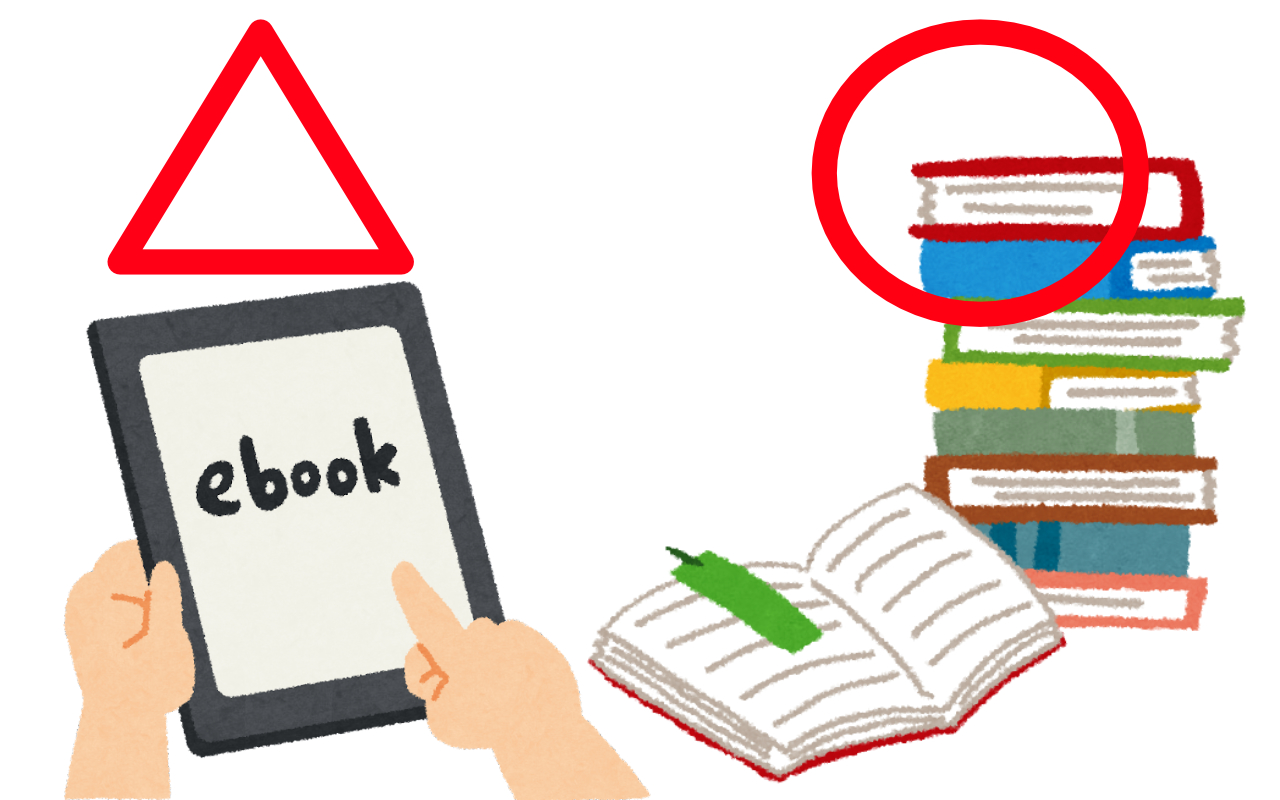
Amazonで読みたい本を検索すると電子書籍化された本だとkindle版を勧めてくることが多くなった。
すぐにでも読みたい本や月額1,960円のサブスクライブKindle Unlimited に含まれている本ならKindleで読むことも悪くないと思う。
実際にKindle版で買って読んだ本もあるしKindle Unlimitedに加入していたこともある。
今はほとんどKindleで読むことはなくなった。
理由はいくつもある。最大の理由は紙の本は所有できるが電子書籍は所有できないことだ。
電子書籍の場合お金を払って読む権利を手に入れているにすぎない。
だから何らかの理由で電子書籍のアカウントを喪失したら、それまでに買った本が全く読めないことになる。
この点紙の本は物理的に失わない限り無くならない。
読書体験という意味でも紙の本には利点がある。
人間は五感によって多くの体験を手にするのだが、電子書籍はほぼ視覚に限定される。たしかにデジタル機器としての手触りがあるが、それはどの本を読んでも機器は同じなので手触りと本との関係は絶たれている。つまり触覚的には違いがない。
今はオフセット印刷ばかりになっているが、以前は活版印刷だったので活字の凹凸があった。手で触れると微妙にその凹凸を感じていたものだ。
紙の質にも違いがあるし、何より本の大きさや重さ、装丁の違いなど見た目だけでなく触覚でも本を楽しむことが出来る。
人の記憶がどのように形成されるかわからないが、例えばある本の中に書かれていたという記憶がある場合、たしか本の右のページの中ほどに書かれていたと思い出すことがある。
その記憶を手掛かりに本をめくると確かに該当の部分に行きつくことがある。
電子書籍ではこの位置感覚がない。
同じ読むという行為でも、紙の本と電子書籍では私たちの認知に大きな違いがあるという研究もあるようだ。

「デジタルで読む脳×紙の本で読む脳」にはその研究の一端が紹介されている。
学生を二つのグループに分け、同じ短編小説を紙の本とKindleで読んでもらいその内容を聞いたところ、紙の本で読んだ学生の方がKindleで読んだ学生より筋を時系列順に正しく再現できたそうだ。
私たちは時間と空間のどこにいるのかを認識しながら生きている。そのためには全体像が不可欠だ。
ところが電子媒体では全体の枠組みがはっきりしないので自分の立ち位置がわからなくなる。
こうした物理的認識の衰退が影響しているのかもしれないというのだ。
紙の本の良さは視認性にある。左右のページが一覧できるだけだけでなく、どの程度読み進んでいるのか、あとどれくらいで読み終わるのかもページの厚みでおおよそわかる。
電子書籍でも何分で読み終えるかが表示されるが、時間で表示されてもピンとこない。
他にも紙の本は書架に並べて背表紙を見るだけで本の目録が一発でわかるというメリットがある。だから本棚の前に立つだけで本のありかがすぐにわかる。気になる本が目に付くといつでも手に取って読むことも出来る。
Kindleの場合、これが難しい。もちろん本のリストは表示されるが数百冊を超えると探すのも大変だ。
紙の本にもデメリットはある。単行本は場所をとる。都市部に住んでいて部屋が狭いとそれほど多くの本を置けないし、家族がいると本が場所ふさぎになるといわれることもあるだろう。
数千冊の本を所有することが出来る人は、本のための空間を持てる贅沢を味わっているといえるのかもしれない。
その点電子書籍は端末だけだ。場所も取らず重くもない。特に大部の本(500ページを超える本)でも気軽に手に取って読める。外に持ち出すのも簡単だ。しかもすぐに読みたい本なら即座にダウンロード可能だから本の到着を待たずに読むことが出来る。
紙の本を読むことに大きなメリットを感じているが、電子書籍の良さを否定するわけではない。
上手に使い分ければ双方のメリットを活かせると思う。