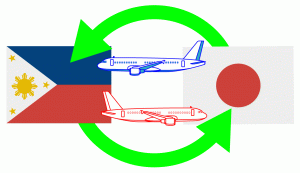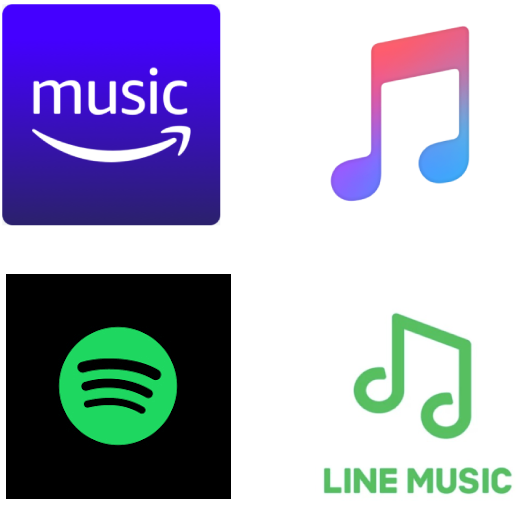
音楽配信サービスのAmazon music HD に加入したのは熊本で学生時代の後輩(先日のブログでは友人と表現したが、今回は年代の違いを表したいので後輩とした)と話したことがきっかけだ。その時に音楽についても話が出た。
去年話題になった映画「ボヘミアン・ラプソディ」についての評価はともかく、後輩の世代にとってクイーンは格別の存在で、1975年4月25日九電記念体育館で行われたコンサートに高校生ながらチケットを買って行ったと話していた。
1975年といえば私は大学に入ったばかりで音楽は小椋佳や井上陽水や吉田拓郎などを聞いていて、クイーンの存在すら知らなかった。
レコードプレイヤーを買ったという話も出たが、それはCDになっていないレコードを聴くためらしい。そんな話をしながら以前読んだ本のことを考えていた。
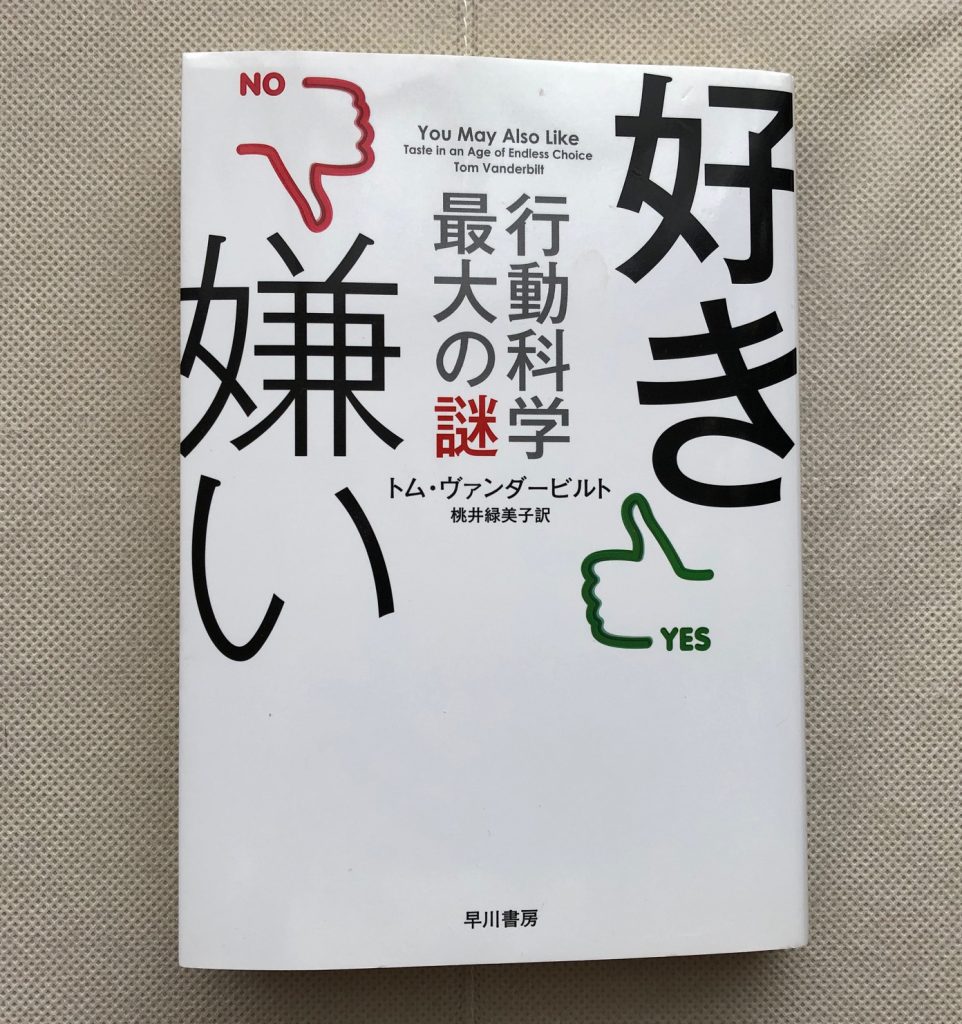
その本はトム・ヴァンダービルトが書いた「好き嫌い-行動科学最大の謎」(早川書房刊)だ。
あらためて本棚から取り出して、「第3章 好みは予想できるか」を読み返してみた。この章は音楽の好みについて書かれている。
「音楽の趣味ほど、その人の『階級』をあらわにし、間違いなく分類するものはない」とフランスの社会学者ピエール・ブリュデューは1979年に発表した本に書いているそうだ。
1979年といえば私が大学を卒業した年なので状況は変わっていると思う。ところがフェイスブックで好みの音楽のジャンルには高級さを感じさせるクラシックやジャズというものが多いらしく、インディーズやダンスミュージックというのはないらしい。
音楽配信サービスの無料体験を申し込む人の多くがほとんど何も聴かないらしい。何千万曲もあるというのに。
でもそれを私が笑うことはできない。Amazon music HDは7,000万曲が聴き放題とある。私が検索して聴いているのは過去に聴いたことがある曲ばかりだ。しかもその過去は私が10代から20代に聴いたもの。
こうした年代の曲が好みになっているのは「レミニセンスピーク」と呼ばれる現象で、記憶に残るほどの衝撃を受ける出来ごとや変化が起こるのが青年期と若年成人期なので、そのころ聴いた音楽が後々まで影響を与えるらしい。
どんな音楽が好きになるのかは、その音楽との出会いだけでなく、その音楽をどのくらい多く聞いたかにもかかわってくる。より多く耳にした音楽をいつの間にか好きになる。耳になじむと好きになる可能性が高いということだ。
7000万曲という音楽の大きな海原に漕ぎ出す勇気があれば、もっと私のお気に入りの音楽が増えそうな予感がする。